SHLグローバルニュース
このコーナーは、イギリスのSHLグループがお客様に向けて発信している様々な情報を日本語に翻訳してご紹介するものです。主にグループの広報誌やユーザー向けネット配信、HPプレスリリースなどから記事をピックアップしています。海外の人事の現場でどんなことが話題になっているのか、人材マネジメントに関して海外企業はどんな取り組みをしているのかをお伝えすることで、皆さまのお役に立てればと願っております。
今回は第121回で取り上げたSHLグローバル・アセスメント・トレンド調査結果について、アメリカ人事コンサルタントChina Gorman氏がそのブログで紹介している記事を取り上げます。
第125回 人事優先課題とビジネス・バリュー
SHLがグローバル・アセスメント・トレンドに関する毎年の報告書を発表しました。SHLはアセスメント会社ですので、アセスメント・トレンドに関する調査報告は最も得意とするところです。調査データは興味深く、その結論は人事に関わる誰もが注目すべきものでしょう。
しかし、調査の問いと結論はアセスメントツールの利用というテーマをはるかに超え、採用や能力開発の戦略・実施に及びます。
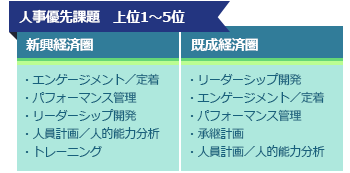 報告書の第一部では組織の人材マネジメントの焦点と展望をレビューしています。例えば、筆者は新興経済圏と既成経済圏の人事優先課題上位5位を比較しています。
報告書の第一部では組織の人材マネジメントの焦点と展望をレビューしています。例えば、筆者は新興経済圏と既成経済圏の人事優先課題上位5位を比較しています。
挙げられているものは似ていますが、全く同じではありません。4つは両方に載っていますが、優先順位が異なります。そして、承継計画が既成経済圏のリストにあることに対し、新興経済圏のリストにはトレーニングがはいっています。
他にはビッグデータの人事活用に関連する結果があり、客観データを使って人事の意思決定を下すことには世界中で改善の余地があるという見解が述べられています。実際、「自社は社員ポテンシャルを明確に理解している」としたのは調査回答者の25%以下でした。
報告書の第二部は、採用と能力開発両方での人材アセスメントに焦点を当てています。このセクションでの興味深い結果には、回答者のほぼ75%が人材測定を改善し、雇用前後のテスト実施を具体的な事業成果に関連付けたいと考えていることが含まれます。
報告書の第三部はテスト実施のテクノロジー、特にモバイルツールとソーシャルメディアに焦点を当てています。ここでの重要な結果は、新興経済圏で、採用側と受検者の両方が、受検者のアセスメントにモバイル技術を使いたいと考えていることです。そして、ソーシャルメディアのデータが雇用決定に関して持つ重要性が薄れつつあります。
報告書は2013年度の人事に対する4つの提言で締めくくられています。
- ビッグデータは、人事がビジネスバリューを示すユニークな機会を提示している。
- 正しいデータのみが人事施策の成功につながる
- 人事は人材採用の方法を改善するイノベーションを(慎重にではあるが)受け入れている。
- モバイル技術は、大勢に従うのではなく、競争上の利点になるかどうかで検討されるべきである。
報告書のデータはわかりやすく、かつ、役立つように提示されています。30ページで、ざっと眺めてインパクトのあるセクションを読み込むのにかかるであろう45分間分の価値はあるでしょう。私は特に巻末の関連文献と、2009年〜2011年の同調査報告書の主要結果まとめを面白く読みました。この種のリストの進化に常に関心を持っています。
しかし、私にとって肝心なことは、人事がそのビジネスバリューをどのように示すかを明らかにすることに、このようなグローバル人事データが光を当てるということです。人事戦略・戦術をビジネス成果に沿わせることのみが、ビジネスバリューを示す唯一の方法です。そして、人事専門家がビジネスリーダーとして見なされる唯一の方法なのです。
(© SHL. Translated by the kind permission of SHL Group Ltd. All rights reserved)
訳者コメント
前回(本コラム第121回)はプレスリリースの記事で、いわばSHLからの視点で調査結果を紹介したものでした。一方、今回は米国の現場第一線プラクティショナーの視点から調査結果を考察したものと言えるでしょう。
調査報告書の本文はここから入手できます。画面上で申請フォームへのご記入が必要ですが、記入によって何らかの義務が発生することは全くありませんので、どうぞお気軽にごご活用ください。
バックナンバー
- 第399回 大卒者の採用と育成:成功の道筋
- 第398回 公平な競争の場の実現を支援する
- 第397回 事例:One Mount〜ハイポテンシャル人材の発掘・育成
- 第396回 AI採用ツール導入時に検討すべき4つの重要なポイント
- 第395回 学習文化を築くための5つのステップ
- 第394回 職場におけるニューロダイバーシティの知見
- 第393回 未来のスキルのための人材・キャリア戦略
- 第392回 SHLが東南アジアでの拠点を拡大
- 第391回 事例:イギリス海軍〜リーダーの異動と能力開発
- 第390回 異なる文化間で公平なアセスメント
- 第389回 2024年の人材展望:人事の未来をナビゲートする
- 第388回 事例: NAVITASYS〜次世代リーダーの発掘と育成
- 第387回 インクルーシブな職場への障壁を打ち破る
- 第386回 貴社コンピテンシーは予測不能な世界に適しているか
- 第385回 ハイポテンシャル従業員の発見にAIを使う
- 第384回 休暇の心理学
- 第383回 知的能力テストはやはり意味があるのでしょうか?
- 第382回 SHLのMobilizeが「最も革新的なタレントマネジメントソリューション」を受賞
- 第381回 いま最も求められている『パワースキル』をSHLが調査
- 第380回 事例:KBC銀行 〜採用コスト90%削減と応募者体験の向上
- 第379回 SHLが2023年World Changing ideas Awardsのファイナリストに
- 第378回 SHLにおけるChatGPTとタレントアセスメント
- 第377回 SHLがディストリビューターの日本エス・エイチ・エルを買収
- 第376回 事例:Wes 〜リーダーシップのダイバーシティ〜
- 第375回 事例:SASRI(南アフリカサトウキビ研究所)後継者育成
- 第374回 グレート・リターン――早期退職者の再就職がもたらすメリット
- 第373回 SHL白書『面接エクスペリエンスの実態(2022)』(4/4)
- 第372回 SHL白書『面接エクスペリエンスの実態(2022)』(3/4)
- 第371回 SHL白書『面接エクスペリエンスの実態(2022)』(2/4)
- 第370回 SHL白書『面接エクスペリエンスの実態(2022)』(1/4)
- 第369回 面接官10人中8人が、貴社の採用ブランドを傷つけている!
- 第368回 タレントアセスメントの妥当性は誇張されている?
- 第367回 リーダー異動の鍵はコンテクチュアル・アプローチ
- 第366回 後継者計画が成功するためのベストプラクティス
- 第365回 進化する職場で成功するために、自分のパーソナリティを変えるべきか?
- 第364回 Purple TuesdayとSHL のニューロダイバーシティ研究プログラムの最新情報
- 第363回 従業員の能力開発とエンゲージメントのために、3つの会社がSHLの『HiPoソリューション』を選んだ理由
- 第362回 事例:BTエンタープライズ
- 第361回 DXは仕事への人間中心アプローチを向上させることができるか?
- 第360回 ハイポテンシャル人材の識別
- 第359回 メタ職場での一日
- 第358回 事例:コンタクトセンター採用
- 第357回 魅力で攻める:オフィスに戻るよう、組織は従業員をどう説得しているか
- 第356回 事例:ITサービス 大卒採用ソリューション
- 第355回 SHLがSHLラボを立ち上げ――人材イノベーションに3000万ドルを投資
- 第354回 コンピューター適応型テスト(CAT)は常に優れているのか?
- 第353回 SHL白書『コロナ禍は私たちの適応力と回復力をどのように変えたか?』(3/3)
- 第352回 SHL白書『コロナ禍は私たちの適応力と回復力をどのように変えたか?』(2/3)
- 第351回 SHL白書『コロナ禍は私たちの適応力と回復力をどのように変えたか?』(1/3)
- 第350回 オンデマンドアナリティクスは人材データを知見に変えるのにどのように役立つか
- 第349回 女性管理職の燃え尽き症候群を減らす3つの方法
- 第348回 メタバースはポテンシャルの見分け方をどのように変えるか
- 第347回 2022年の新卒採用についてあなたが知っておくべきこと
- 第346回 今すぐ新卒採用をすべき10の理由
- 第345回 組織のリーダーは『イカゲーム』から何を学べるか?
- 第344回 2022年により良いリーダーになる方法
- 第343回 キャリアモビリティと能力開発が、大量自主退職時代の問題をいかに解決できるか?
- 第342回 事例:NOKIA 将来の戦略的コンピテンシーの測定と育成
- 第341回 中東におけるユニコーン新興企業の台頭
- 第340回 事例:コスタクルーズ社のリモートワークへの移行をSHLが支援
- 第339回 仕事のパフォーマンスを高める、ディワリからの学び5選
- 第338回 事例: リーダーシップポテンシャルを解き放つ――バーチャル・アセスメント&ディベロップメントセンター
- 第337回 貴社の大学新卒採用を際立たせる方法
- 第336回 拡張知能がビデオ面接の評価にどのように役立つか
- 第335回 2021年度 日本エス・エイチ・エル 学会発表のご報告
- 第334回 セールストランスフォーメーションに影響を与える3つの外部要因
- 第333回 事例: 大手通信会社が質の高いソフトウェアエンジニアの採用にかかる時間を70%低減
- 第332回 事例: IT人材採用―AIを活用したコーディングシミュレーション
- 第331回 バタフライ効果−新型コロナウィルスがどのように新卒採用を変えたか
- 第330回 テクノロジーがDEI施策に真の変化をもたらす(3/3)
- 第329回 DEI施策で真の変化を起こす方法(2/3)
- 第328回 ダイバーシティ推進に総合的に取り組むための3つの戦略(1/3)
- 第327回 ローカライゼーションの話
- 第326回 IT人材採用において技術的スキル以外のスキルを評価することの重要性
- 第325回 ニューロダイバーシティ採用:受検者の体験を理解するための研究
- 第324回 2021年、タレントモビリティは不可欠に
- 第323回 採用用パーソナリティ検査の真実を明らかにする
- 第322回 優れたIT人材を採用するための4つのポイント
- 第321回 採用と人材マネジメントはどのように変わったか
- 第320回 事例:Cundall – ハイポテンシャルソリューション
- 第319回 SHL白書:Z世代のリーダー志望者は何を提供できるか?(3/3)
- 第318回 SHL白書:Z世代のリーダー志望者は何を提供できるか?(2/3)
- 第317回 SHL白書:Z世代のリーダー志望者は何を提供できるか?(1/3)
- 第316回 事例:Axis Bank - 大量選抜ソリューション
- 第315回 リモートチームのマネジメント:リモートワークは長くなりそう
- 第314回 よいオンライン面接体験を促進する5つの方法
- 第313回 SHL Smart InterviewがマイクロソフトTeamsやZoomと統合
- 第312回 モバイル・ファーストの採用プロセスに関する検討点
- 第311回 会社が採用を行っていないとき、どうやって素晴らしい採用担当者であり続けることができるか?
- 第310回 事例:ネーションワイド・ビルディング・ソサエティ−組織変革にデータでインパクト
- 第309回 SHLバーチャル・アセスメント&ディベロップメントセンターが、最も革新的なソリューションとしてHRテック賞を受賞
- 第308回 タレントマネジメントの進化
- 第307回 事例:ブリストル&ウェストン大学病院(NHS財団トラスト)
- 第306回 我々のお客様は人材戦略をどのように再考しているか
- 第305回 ある地域信用組合の新任CEOへの情報提供をSHLが支援
- 第304回 新卒採用における冒険
- 第303回 事例:GKNエアロスペース リーダーシップ開発
- 第302回 パンデミック後の復興の準備を始める時
- 第301回 平常でない時に、リモートワークを平常に感じさせる方法
- 第300回 必要不可欠なものは何か? 難しい時に大きな疑問を問う
- 第299回 遠く離れていると感じますか? 生産性を保つための、リモートワークのベテランからの5つのコツ
- 第298回 RemoteWorkQ:あなたのチームを、サポートされた生産的なリモート・ワークフォース(遠隔勤務の集団)に移行する
- 第297回 SHLのビデオ面接ソリューションが世界の労働者を結びつける
- 第296回 貴社のリーダーは世界規模パンデミックという問題に対する準備ができていますか?
- 第295回 産業組織心理学者という職業
:SHLサイエンス・アワード初開催 - 第294回 新しい年、人事が「止めるべきこと」「始めるべきこと」「引き続きやるべきこと」
- 第293回 SHLがKenexaタレント・アセスメントについてIBMとパートナーに
- 第292回 ベストのものがより良く:SHLが旗艦製品OPQをリイマジン
- 第291回 応募者をぐっと惹き付けるための4つの重点エリア
- 第290回 ベストな学生からベストを選ぶことに成功したUSBの秘密
- 第289回 AIアセスメントの4つの原則
- 第288回 デジタル時代、人材戦略が極めて重要な中、SHLがAspiring Minds社の買収を合意
- 第287回 結婚しましょう!適切なアセスメント・パートナーを選ぶ
- 第286回 ベストのものがより良く:SHLがOPQを再開発
- 第285回 Human Resource ExecutiveがSHL Verify Interactiveに2019年トップHR製品賞を授与
- 第284回 ニューヨークからシドニーまで、SHLがコミュニティにお返し
- 第283回 応募前の段階でベストフィットの応募者を惹きつける3つの方法
- 第282回 祖父の時代の知的能力テストとは違う
- 第281回 事例:ソニック・オートモーティブ社――採用ソリューション
- 第280回 産業組織心理学者が仕事の未来を形作る3つの方法
- 第279回 ケルヒャー
- 第278回 デジタル人材不足という通説
- 第277回 SHLが新生1周年を祝し、SIOP 2019にて革新的な新商品SHL Verify Interactive を発表
- 第276回 Culture FitかCulure Addか
- 第275回 デジタル人材にとっては、「誰が」よりも「どのように」が重要
- 第274回 効果的なコンピテンシーモデルを作る5つのこつ
- 第273回 リーダーシップ見極めの事例:カンパリ
- 第272回 HIPOソリューション事例:ブリストル・マイヤーズ スクイブ
- 第271回 貴社ビジネスの将来のために人材をアセスメントする
- 第270回 事例:Genea――エンタープライズ・リーダーシップ・ソリューション
- 第269回 採用戦線で勝てる応募者体験を実現する3つのポイント
- 第268回 事例:デル
- 第267回 ダイバーシティとインクルージョン
- 第266回 事例:パールメディア
- 第265回 クリスマスシーズンに向けての店員採用
- 第264回 機械学習は人間のバイアスを取り除くことができるのか?
- 第263回 アジリティとダイバーシティとデジタル化に共通するものは?
- 第262回 事例−キンバリークラーク:アセスメントで大きなコスト削減を実現
- 第261回 ジェンダー・ダイバーシティの促進:リーダーシップ・チャレンジにおいて女性がリード
- 第260回 事例:FSCS ハイポテンシャル者の発見と育成
- 第259回 採用の意思決定を改善するための、避けるべき3つの間違い
- 第258回 事例:ボンバルディア
- 第257回 大学新卒採用への新しいアプローチ
- 第256回 事例:E.ON
- 第255回 2018年グローバル・アセスメント・トレンド調査――エグゼキュティブ・サマリー
- 第254回 事例:アデコ・グループ――SHL Leader Edge Solution
- 第253回 SHL白書「タレント・アセスメント・テクノロジーの台頭」(連載6)――結論と提言
- 第252回 SHL白書「タレント・アセスメント・テクノロジーの台頭」(連載5)――メディア形式について
- 第251回 SHL白書「タレント・アセスメント・テクノロジーの台頭」(連載4)――シリアスなゲーム
- 第250回 SHL白書「タレント・アセスメント・テクノロジーの台頭」(連載3)――ゲームの手法を応用したアセスメント
- 第249回 SHL白書「タレント・アセスメント・テクノロジーの台頭」(連載2)――新しいアセスメント・テクノロジーを吟味する
- 第248回 CEB白書「タレント・アセスメント・テクノロジーの台頭」(連載1)
- 第247回 貴社のリーダーシップ戦略を革新するための4つの原則
- 第246回 優れた採用
- 第245回 職場におけるテクノロジーの未来について
- 第244回 事例:アムジェン
- 第243回 必ずしもあなたが答えを持っている必要はありません。誰が持っているかを知っていればよいのです。
- 第242回 管理職によるコーチングに対する期待を再考する
- 第241回 リーダーは燃料切れ? なぜ文脈が重要なのか?
- 第240回 リーダーシップについて、人事がより良い意思決定を行う3つの方法
- 第239回 カーギル社のパフォーマンスマネジメントは何故優れているのか?
- 第238回 グローバル労働市場は雇用される側に有利
- 第237回 ダニエル・カーネマンが意思決定のし方について語る
- 第236回 サンダーランド市
- 第235回 学びの文化の重要性
- 第234回 会社の人材アセスメントを改善する(さらに)5つのステップ
- 第233回 会社の人材アセスメントを改善する5つのステップ
- 第232回 Z世代人材の採用戦線で勝つために人事は何ができるか?
- 第231回 事例:オーチス 社員の教育研修
- 第230回 成長マインドセットを使って学びを刺激
- 第229回 人材アセスメントツールの革新的な使い方
- 第228回 ユナイテッド航空、失態後の方針変更
- 第227回 あなたは人材を怖がらせて遠ざけてはいませんか?
- 第226回 人材分析の事例:ギャップ社
- 第225回 社員のメンタルヘルスと健康を会社がどうサポートできるか?
- 第224回 テストをテストする:人材アセスメントに関する5つの誤った俗説
- 第223回 笑顔の数が生産性の指標?
- 第222回 ハイポテンシャル者についての誤解がプログラムを危険にさらす
- 第221回 事例:バルメット
- 第220回 なぜディベロップメントセンターを使うべきなのか?
- 第219回 ハイポテンシャル人材に対して、彼らが将来のリーダーだと告げる理由
- 第218回 トランプ氏大統領就任が米国企業人事に及ぼす影響
- 第217回 CEB CEO トム・モナハン
- 第216回 事例:ノボノルディスクがリーダーシップ・パイプラインを強化
- 第215回 変革マネジメントを機能させる(2/2)
- 第214回 変革マネジメントを機能させる(1/2)
- 第213回 コンピュータセンター社
- 第212回 なぜ人は仕事を辞めるのか
- 第211回 HIPOプログラムをどう改善できるか
- 第210回 事例:スイス陸軍士官学校
- 第209回 第32回産業・組織心理学会大会報告
- 第208回 全ての従業員エンゲージメント調査で尋ねるべき9つの質問
- 第207回 IT専攻学生以外をねらえ
- 第206回 Brexitから派生する人事問題(後編)
- 第205回 Brexitから派生する人事問題(前編)
- 第204回 事例:イタリア本社の大手保険会社ゼネラリがマネジャーの見極めと能力開発にSHLを使用
- 第203回 リーダーシップ開発が職務上でなければならない理由
- 第202回 事例:DHL ジョブ・マッチングとディベロップメントセンターで組織再編成
- 第201回 事例:ベルデン 営業力強化
- 第200回 面接4回は止めよう
- 第199回 事例:ウェバー・ウェンツェル法律事務所(南アフリカ)
- 第198回 CEB白書:リクルーターを人材アドバイザーとして再定義する(5・完)
- 第197回 CEB白書:リクルーターを人材アドバイザーとして再定義する(4)
- 第196回 CEB白書:リクルーターを人材アドバイザーとして再定義する(3)
- 第195回 CEB白書:リクルーターを人材アドバイザーとして再定義する(2)
- 第194回 CEB白書:リクルーターを人材アドバイザーとして再定義する(1)
- 第193回 事例:マイクロソフト
- 第192回 2016年、人事にとって人材分析がなぜ一番の優先課題なのか?
- 第191回 ハイ・ポテンシャル・プログラムの3大リスク−対応策
- 第190回 ハイ・ポテンシャル・プログラムの3大リスク
- 第189回 人事考課をやめたいですか?もう一度考えてください。
- 第188回 アクセンチュアが毎年の人事考課とランキングを一掃
- 第187回 カンパリ・グループ
- 第186回 エンタープライズ・リーダー(3/3)
- 第185回 エンタープライズ・リーダー(2/3)
- 第184回 エンタープライズ・リーダー(1/3)
- 第183回 第31回産業・組織心理学会大会報告
- 第182回 私の最初の90日間:新リーダーは一人では成功できない(し、すべきではない)
- 第181回 リーダーシップに関する5つの質問:ビッキー・ハンプソン(ピアソンplc. Sales and Customer Excellence SVP)
- 第180回 エンタープライズ・リーダーをどう育成するか?
- 第179回 正しい企業イメージをブランディングする
- 第178回 ミレニアル世代は火星から来たのではありません
- 第177回 ミレニアル世代のマネジメント――虚構と現実を分ける
- 第176回 ジョゼ・モウリーニョ――ビジネスリーダーの新モデル
- 第175回 シンデレラに学ぶ5つのレッスン
- 第174回 イノベーターのDNA
- 第173回 本社は耳を傾けているか?
- 第172回 事例:ハイネケン グローバル新卒採用
- 第171回 人材測定の効果――(5)ビジネス・アウトカム・スタディ(後編)
- 第170回 人材測定の効果――(4)ビジネス・アウトカム・スタディ(前編)
- 第169回 人材測定の効果――(3)ビジネスバリュー・ステートメント(事例後編)
- 第168回 人材測定の効果――(2)ビジネスバリュー・ステートメント(事例前編)
- 第167回 人材測定の効果――(1)はじめに
- 第166回 2015年、人事はこの5つの優先事項を見逃すな
- 第165回 Y世代は良いリーダーになれるか?
- 第164回 事例:アダブ・トラスト――ダイバーシティと雇用機会均等を改善
- 第163回 世界の会社員は仕事に何を求めているか?
- 第162回 採用場面におけるゲーミフィケーションの活用――トレンドとベストプラクティス
- 第161回 新卒者の3分の2が最初の職を後悔
- 第160回 事例:ウェストヨークシャー州消防局
- 第159回 事例:オーストラリア ビクトリア州司法局
- 第158回 ネガティブ経験への対処なし
- 第157回 モバイル・アセスメント:長所と短所
- 第156回 HRのサバイバル的考え方がビジネスの成長を阻害
- 第155回 CEBがThe Economic Timesと協力して、インドの次世代リーダーを見極め
- 第154回 サイコメトリックスのパワー(2/2)
- 第153回 サイコメトリックスのパワー(1/2)
- 第152回 CEBが今年の採用技術革新賞を受賞
- 第151回 ハイポテンシャル人材識別のためのHRガイド
- 第150回 ハイポテンシャル人材とはどんな人材か?
- 第149回 CEBが中国で人材マネジメント業界リーダーとして認められる
- 第148回 社員調査を再考する‐エンゲージメントを超えて(3/3)
- 第147回 社員調査を再考する‐エンゲージメントを超えて(2/3)
- 第146回 社員調査を再考する‐エンゲージメントを超えて(1/3)
- 第145回 ビジネスの成功を推進する人材戦略
- 第144回 事例:スワロフスキー
- 第143回 企業戦略・プロジェクト切り上げの難しさ
- 第142回 まずいオン・ボーディングの隠れたコスト
- 第141回 ネルソン・マンデラ氏の残したもの
- 第140回 幹部候補者トレーニングに不信
- 第139回 事例:マークス&スペンサー
- 第138回 CEBリポート:グローバル・リーダーシップ・パイプラインの強化(3/3)
- 第137回 CEBリポート:グローバル・リーダーシップ・パイプラインの強化(2/3)
- 第136回 CEBリポート:グローバル・リーダーシップ・パイプラインの強化(1/3)
- 第135回 人事リスク上位8位と、その対処方法(後半)
- 第134回 第29回 産業・組織心理学会大会報告
- 第133回 人事リスク上位8個と、その対処方法(前半)
- 第132回 事例:国際連合のコンピテンシー採用
- 第131回 新卒採用者にとっての難問‐SHLグローバルスタディより
- 第130回 新入社員がチームをかき回すのをどうやって止めることができますか?
- 第129回 事例:質の高い成長のためにブランドのスターを見極め――インターコンチネンタル ホテルズ グループ
- 第128回 2013年度ビジネス成果研究リポート 主な結果
- 第127回 2013年度ビジネス成果研究リポート 研究手法
- 第126回 2013年度ビジネス成果研究リポート――アセスメント・ソリューションによる収益改善――
- 第125回 人事優先課題とビジネス・バリュー
- 第124回 SIOP 2013
- 第123回 事例:メッツォ
- 第122回 情報のビジネス的な価値を最大化する
- 第121回 2013年グローバル・アセスメント・トレンド調査報告書
- 第120回 タレント・オーディットでビジネスの成長力を確保する
- 第119回 事例:スイス・リー
- 第118回 雑誌記事 Marriage of Equals
- 第117回 事例:グラクソ・スミスクライン
- 第116回 貴社のビジネスにとって最もリスキーな人は誰ですか?
- 第115回 事例:KPMG
- 第114回 アセスメントを考える
- 第113回 SHL香港が『優秀HRサービス賞』を獲得
- 第112回 事例:カンタス航空
- 第111回 女性は何故、英国企業のトップの位置に登ろうとしないのか?
- 第110回 事例:スワロフスキー〜離職率を下げ、雇用プロセスをブランド化する〜
- 第109回 ヨーロッパにリーダーが足りなくなる
- 第108回 SHLグローバル・リーダーシップ研究結果
- 第107回 中国では採用はソーシャルに
- 第106回 事例:バークレイズ よりよい選抜のための評価者トレーニング
- 第105回 職場におけるダイバーシティの障壁を切り崩す
- 第104回 中国のビジネス・エリートが上海でSHL LINKカンファレンスに参加
- 第103回 事例:ゼロックス
- 第102回 サクセッション・プランニングを効果的に進めるための6つの戦略
- 第101回 あなたの上司は明日も仕事にきますか?
- 第100回 オリンピックで仕事を休めるか?
- 第99回 2012年度グローバル・アセスメント・トレンド調査結果(サマリー)
- 第98回 アセスメント・トレンドの変化〜人材をより大局的に捉える〜
- 第97回 調査・統計ニュースより〜
- 第96回 SHLが南アフリカのリーダーシップ指数を発表
- 第95回 コア・バリューに沿った採用プロセスを:ジョン・ルイスとHSBCの事例
- 第94回 人材をめぐる戦い:here and now
- 第93回 事例:ユニリーバ 大卒採用
- 第92回 事例:タレス・アレーニア・スペース
- 第91回 大学4年生のための職探しのヒント
- 第90回 事例:テスコ――新設職の評価プロセスをSHLと共同で開発
- 第89回 パーフェクトなパーソナリティを採る――アセスメント・テストの人気高騰
- 第88回 ごめんなさい。コンピューターが「だめ」と言っています。
- 第87回 事例:DHLサプライチェーン 大卒採用
- 第86回 起業家新世代の創造をSHLが支援
- 第85回 SHLがビジュアル・アイデンティティを一新
- 第84回 事例:ヒルトン・インターナショナル
- 第83回 ビデオクリップを用いた面接者要因の探索的研究(学会発表報告)
- 第82回 事例:NASA(アメリカ航空宇宙局)
- 第81回 中小企業は採用費を無駄に使っているかも
- 第80回 社員本人が自分自身の最も厳しい批評家
- 第79回 成果研究レポート
- 第78回 事例:日産
- 第77回 グローバル・アセスメント・トレンド調査結果(サマリー)
- 第76回 大卒者の60%が仕事を見つけられていない
- 第75回 SHLクライアントの大卒採用が名誉ある賞を受賞
- 第74回 安全のDNAを分解する(3) 〜職場事故はなぜ起き続けるのか?
- 第73回 安全のDNAを分解する(2) 〜職場事故はなぜ起き続けるのか?
- 第72回 安全のDNAを分解する(1) 〜職場事故はなぜ起き続けるのか?
- 第71回 事例:BUPA
- 第70回 英国労働力の意欲欠如が「幽霊退職」に拍車
- 第69回 顧客調査結果:貴社の人事課題を理解するために
- 第68回 ベストな人材を採用するチャンスをつかめ
- 第67回 SHLとPreVisorが合併――人材マネジメントのグローバル・リーダーへ
- 第66回 事例:ゼロックスU.K.
- 第65回 SHL社ユージーン・バーク氏がテスト出版社協会の理事に選出される
- 第64回 事例:イギリス航空管制公社(NATS)――オンライン採用選抜プロセスを改善
- 第63回 ロンドン人はイギリスで最も勤勉でやる気にあふれた労働者である
- 第62回 組織の成長のためのオン・ボーディング(2)−実務上のヒント
- 第61回 組織の成長のためのオン・ボーディング
- 第60回 iPQを発売
- 第59回 事例:富士通のタレントマネジメント
- 第58回 2011年大学卒業予定者は、企業が求める対人スキルに欠けている
- 第57回 SHL顧客にとってアセスメントが事業業績にプラス影響(アバディーン調査結果)
- 第56回 まずい採用方法のせいでビジネスが顧客を失うかも(その2−小売業界編)
- 第55回 まずい採用方法のせいでビジネスが顧客を失うかも
- 第54回 SHLグループCEOへの質問
- 第53回 事例:ケロッグの人材マネジメントプログラムにSHLがパリン、パチパチ、ポンを追加
- 第52回 採用業務アウトソーシング
- 第51回 ネットワーキングの科学−SHLシニアコンサルタント Alex Fradera
- 第50回 事例:ハーツ−変革を推進する人材を選抜
- 第49回 「いい気にならずに適合度を」SHL CEO ディビッド・リー
- 第48回 キネティク社−南極探検隊メンバー選抜
- 第47回 SHLが中国に上海オフィスを開設、ATAとパートナーに。
- 第46回 最先端のテクノロジーを維持する
- 第45回 パーソナリティ検査の投資収益
- 第44回 大量採用
- 第43回 LinkedInのSHLグループに参加しませんか?
- 第42回 2010年DOP大会にて
- 第41回 将来に目を向ける時が来た
- 第40回 事例:コールセンター・顧客サービスのスタッフ採用(2)
- 第39回 事例:コールセンター・顧客サービスのスタッフ採用(1)
- 第38回 EU大統領の選出方法はおかしい、とSHLが警告。
- 第37回 約600万人のイギリス労働者が職務に満足していない
- 第36回 SHLが画期的なパーソナリティ検査を発売
- 第35回 技術投資によってより迅速な人事決定が実現
- 第34回 事例:クリスピー・クリーム・ドーナツ
- 第33回 客観採点式インバスケットテストの開発と妥当性検証(学会発表報告)
- 第32回 不況下における社員エンゲージメント・意欲低下の背景について、重要な洞察をSHLが公開。
- 第31回 ケーススタディ:オックスファム
- 第30回 ケーススタディ:3M
- 第29回 社員は『昇進』と『能力開発』の機会に欠けていると認識
- 第28回 SHLに新CEO
- 第27回 ケーススタディ:シェル石油開発
- 第26回 ケーススタディ:オイルサーチ社
- 第25回 動機付けに「万能の」やり方はない、とSHLが警告
- 第24回 求職者の4分の1が仕事を得るためにうそをつく
- 第23回 SHLが次のルイス・ハミルトン探しを加速
- 第22回 SIOP大会でSHLアンディ・ロス博士が講演
- 第21回 第24回SIOP大会にSHLが参加
- 第20回 チームビルディング
- 第19回 ケーススタディ:大手国際銀行A行
- 第18回 SHLとStepStoneが業務提携
- 第17回 ケーススタディ:ソニー・ヨーロッパ
- 第16回 ケーススタディ:アライアンス・ユニケム
- 第15回 年齢とOPQの関係に関する最新研究
- 第14回 あなたはどんな学習パーソナリティをもっていますか?SHLにお尋ねください。
- 第13回 今日のグローバル経済における人材
- 第12回 ケーススタディ:イギリス国営くじ基金(3)
- 第11回 ケーススタディ:イギリス国営くじ基金(2)
- 第10回 学会発表ご報告
- 第9回 ケーススタディ:イギリス国営くじ基金(1)
- 第8回 ケーススタディ:イギリスリバプール市
- 第7回 客観テストに関するヨーロッパ企業調査結果
- 第6回 リーダーが足りなくなる!
- 第5回 採用シンポジウム(東京)報告
- 第4回 大学院生への研究支援
- 第3回 ケーススタディ:コカ・コーラ
- 第2回 言葉よりも行動
- 第1回 Y世代は、採用にどんな影響を与えるのか?
